![]()
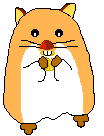

![]()
![]()
![]()
![]()
| ウイルスは生きた細胞の中でしか増殖することができず、生物と言えそうで言えない小さな小さな粒子(サッカーボールをウイルスとすれば、人間はほぼ地球の大きさ)です。ウイルス粒子はDNAまたはRNAと呼ばれる遺伝子がタンパク質におおわれたかたちで存在し、人間や動植物の中に入り込んでは増殖を繰り返すことによって自然界の中で生活環を作っています。 |
![]()
![]()
| それではこれらのウイルスがどうして、どのようにして私たち人間に病気をおこすのでしょうか?ウイルスがひき起こす病気といえば、エイズ、インフルエンザ、はしか、水ぼうそう、風疹、おたふくかぜ…皆さんが聞いたことのある病気がたくさんあるのではないでしょうか。そうです、私たちのウイルス部門は、ウイルスがどうして私たちにこのような病気をおこすのかを県民の皆さまとともに考えていく部署なのです。 |
![]()
![]()
| ウイルスが皆さんに感染して病気をおこします。すると私たちは医療機関を通じて患者さんの咽頭拭い液(のどを綿棒で拭ったもの)や便の検体を受け取り、どんなウイルスが患者さんの中でふえて病気をおこしたのかを検査します。たとえば、冬になってインフルエンザが流行した時には、患者さんののどにどのような病原体がいるかを調べます。その結果、1999年から2000年にかけての冬には、県内でAソ連型とA香港型の2種類のインフルエンザが流行していたということがわかりました。また、カキの生食の後に食中毒がおこることがありますが、患者さんの便で検査を行うと、小型球形ウイルスが検出されることが多いのです。 |
![]()
![]()
| ウイルス感染症予防対策としては、たくさんの良いワクチンができ、私たちは医学、医療の進歩の恩恵にあずかっています。しかし、薬剤については、ウイルスに効果がある薬は十分に開発がなされていません。それでも私たちは、いつの日か良い薬ができ、また現在よりもっと良いワクチンができる日を心待ちにしているのです。その前提として、私たちはウイルスがいつ、どこで、どのような病気をおこしているのかを把握し続けなければならないのです。 |
![]()
![]()
| ウイルスの病気の県内での流行状況を把握するため、山形県内では下記の図のように、感染症発生動向調査のシステムが作られています。このシステムが有効に稼働するためには、実際に病気になられた患者さん、医療従事者の皆様などのご理解・ご協力が不可欠なのです。どうか今後とも県民の皆様のご協力を宜しくお願い致します。 |
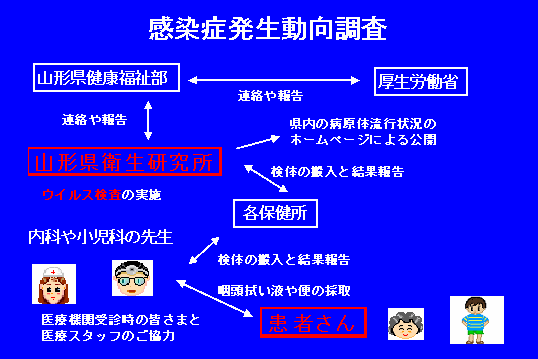 |
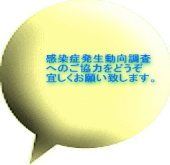 |
|
| 山形県内の感染症発生動向調査の流れ |